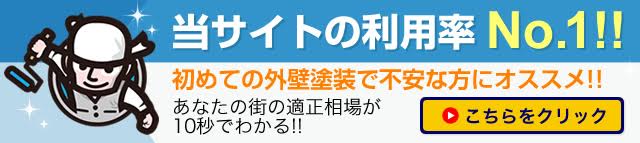
塗装作業が関与する欠陥現象の原因と対策 - 外壁塗装の達人 | 都道府県別で塗装店の費用や特徴を比較出来る!! 外壁塗装の達人 | 都道府県別で塗装店の費用や特徴を比較出来る!!
塗装工事について考える時、塗料の種類や費用にばかり目がいってしまいがちですが、大事なポイントはそれだけではありません。
塗装の作業の仕方が適切でないと欠陥が発生してしまうのです。
その作業の仕方により発生してしまう欠陥は、作業者の技術力不足によるものと言えます。
塗装作業が関与する欠陥現象を把握しておく事で、塗膜の欠陥が生じた際に原因を判断することが出来ます。
塗装作業が関与する欠陥現象について、詳しくご紹介致します。
塗料塗布時に、刷毛やローラーの跡が塗膜に発生することで、縞模様のような凹凸が塗膜に発生してしまう現象です。
刷毛やローラーの使い方が良くないと、刷毛目やローラー目が残ってしまいます。
技術力の高い業者にお願いすれば、余計な刷毛目やローラー目を発生させずに塗装してもらえます。
刷毛やローラーのお手入れが行き届いておらず、堅過ぎたり状態が良くないことで余計な刷毛目やローラー目が発生してしまいます。
刷毛やローラーは使用後に希釈剤を使い丁寧にお手入れをすることで、刷毛やローラーの余計な走りを無くすことが出来ます。
堅い刷毛やローラーを使うと、刷毛目やローラー目が出やすくなりますので、使い古しで硬くなっている刷毛やローラーは処分し、新しいやわらかい刷毛やローラーを使うと良いでしょう。
塗料の粘度が高過ぎたり、顔料の含有率が高過ぎると発生してしまいます。
被着体に合う、顔料の含有率が適切な塗料を使用するようにしましょう。
また、被着体に対し塗料の粘度が高過ぎると刷毛目やローラー目が出やすくなってしまうので、その場合には希釈剤で希釈し粘度を下げると良いでしょう。
高温等により乾燥速度が速くなると、塗膜が異常な乾燥をし、刷毛目やローラー目が発生してしまいます。
その対策としては、蒸発速度の遅い塗料を使用すると良いでしょう。
塗布の際に塗膜上に泡が発生し、そのまま硬化する事でブツブツとした塗膜になってしまう現象です。
規定以上の塗布量で塗布すると厚塗りとなってしまい、あわが発生してしまいます。
厚塗りをせずに規定通りの塗布量を守ることが大切です。
どうしても厚い塗膜を得たい場合は、塗布回数を2~3回に分けて重ね塗りをすると良いでしょう。
塗料は持ち運び等であわが出来てしまうことがあります。
塗布前に泡をしっかりなくして使う事で、塗膜表面にあわを発生させずにすみます。
塗料搬入や持ち運び後はすぐに使わずに、一定の時間を置くと良いでしょう。
また、撹拌後はしばらく放置した後に使用するべきです。
被着体に水分が多いと塗料が被着体と密着できず、あわとして塗膜表面に出してしまいます。
被着体表面に余計な水分が無いかをきちんと確かめてから塗装工程を進めましょう。
被着体が木部の場合、木材の含水率が10%以下の状態でしっかりと目止めをして塗装すると良いでしょう。
被着物の温度が高過ぎると異常な硬化が起こり、塗膜表面にあわが出てしまいます。
夏など高温の日は養生シートなどで被着体の温度を下げてから塗装を行うことで防ぐことが出来ます。
下塗りが不適切だとムラが出来てしまい、しっかりとした目つぶしにならず塗装工程の際にあわが発生してしまいます。
下塗りは塗り残しがないようにムラなく綿密に行うべきです。
下塗りだからある程度塗布していればよいなんていう考え方をする職人さんも居るようですが、それでは簡単にあわが発生してしまうのです。
エアスプレーの空気圧が高過ぎると、噴射する塗料の中に余計に空気が入り、塗膜にプツプツとあわを発生させてしまいます。
それはエアスプレーの霧化空気圧を下げることで解決できます。
ノズルチップを小さい物に替えることでも塗料圧力を下げることが出来ます。
塗料が完全硬化せず、硬化時間が過ぎても塗膜表面がベタベタとしてしまう現象です。
古い塗料は硬化力を失っていることがあり、既定の時間以上放置しても完全に硬化しない場合があります。
塗料には使用期限がありますので、使用期限が過ぎているものは使わないようにしましょう。
ヤニの多い木材に塗布する場合、ヤニの影響で塗膜がきちんと硬化しなくなってしまうことがあります。
事前にヤニ止めをし、ヤニ用のシーラーを塗布することでヤニの影響を受けずに済みます。
厚塗りしすぎると乾燥しにくくなってしまい、いつまでも硬化せず粘度が高い塗膜となってしまうことがあります。
塗料には1度あたりの塗布量が決まっています。
厚めの塗膜を作りたい場合には一度で厚塗せず、何度か分けて重ね塗りをするようにしましょう。
下塗り塗料が乾燥していないうちに次の塗装を行ってしまうと、乾燥していない塗料の水分の逃げ場がなくなり、塗膜が完全に乾燥できなくなってしまいます。
必ず規定の乾燥時間を守った上で次の塗装工程を行うようにしましょう。
塗装工程の中で行った研磨紙刷りの研磨の模様が、その後の塗装工程で隠れずに塗膜表面に現れてしまう現象です。
研磨紙刷りに使うべき研磨紙の番号は決まっており、決まった番号の研磨紙を使うのが鉄則です。
しかし、職人さんの中には早く研磨紙刷りを終わらせたいなどの理由で、番号の低い粗目の研磨紙を使う方もいらっしゃいます。
規定以上の荒い研磨紙を使うと研磨紙による傷が大きくできてしまうため、その上に塗料を重ねてもカバーすることが出来ません。
研磨紙は規定の範囲内の物を使用し、仕上げは番号の高い細かい研磨紙を使って綺麗に仕上げることが重要です。
塗膜厚が薄いと研磨紙の傷をカバーできませんので、塗膜に傷が現れてしまいます。
塗装回数が少なかったり、1回の塗布量が少ない、塗料の希釈のし過ぎなどが原因です。
塗装終了時には平らにきちん塗装をされていたように見えていたが、サイディングなどの継ぎ目に塗料が溜まっており、後で塗料が染み出してたれを作ってしまう現象です。
厚塗りのし過ぎにより被写体の継ぎ目に余計に塗料が滞留し、後にそこから余分な塗料が垂れてしまいます。
規定の塗布量を守り厚塗りしないようにすることで、二次たれを防止できます。
被着体の隙間に不純物が多くあると、塗料を滞留させやすい状態になってしまいます。
エアブローなどで洗浄を丁寧に行って不純物を綺麗に取り除くようにしましょう。
規定の塗布量で塗布したのにもかかわらず、乾燥後十分な塗膜厚を作り上げられていない状態です。
シーラーなどの下地をしっかり塗布していないと塗料が被着体に多く浸透してしまい、塗膜厚が薄くなってしまいます。
シーラーやフィラーなどの下地をムラなくきちんと塗布することで、余計な塗料の吸い込みを防ぐことが出来ます。
塗料を規定以上に希釈しすぎてしまうと、いくら塗布しても厚い塗膜にならなくなってしまいます。
適切な粘度の塗料を塗布することが大切です。
対策としては、2回塗布するのを3回にするなど塗布回数を増やすと良いでしょう。
被着体と塗膜との付着が弱く、剥がれてしまう現象です。
下地が湿っていると付着力が落ち、塗膜が浮いて剥がれてしまいます。
塗料塗布前には被着体の乾燥状態をしっかりと確認しましょう。降雨時や湿度が高い時の塗装工事は避けるべきです。
職人さんの中には小雨なら作業可能と考える方も居るようですが、小雨でも十分に湿度が高いため、しっかりとした塗膜を作ることは出来ません。
被着物表面に油やホコリ等が付着していると被着体と塗膜の間に隙間ができ、密着不良を起こしてしまいます。
塗布前には必ず被着体表面の不純物をきちんと取り除いてから作業を行わなければいけません。
研磨紙刷りが不足していると被着体と塗膜が密着しにくくなり、密着不良になってしまいます。
研磨紙刷りが必要な被着体は念入りに研磨紙刷りを行いましょう。
塗膜厚が薄すぎると密着力が落ち、密着不良になってしまいます。
規定量で塗布するようにしましょう。
また、塗料を希釈しすぎても塗膜厚が薄くなってしまいますので、希釈のし過ぎには注意しなければなりません。
塗料の撹拌不足も塗料の濃度ムラが起きてしまいますので、必ずしっかりと撹拌してから使用しましょう。
塗布時の温度が高過ぎると異常な乾燥が起き、被着体に強固に密着しなくなってしまいます。
夏の高温時での施工の場合は、被着体の温度を下げて塗装を行わなければなりません。
屋外などでは、養生シートなどで温度を下げてから塗装工事を行うようにしましょう。
いかがでしたでしょうか。
このように、塗料の扱い方や技量が不十分だと塗膜に欠陥ができてしまうことがあります。
良い塗料を使用してもそれを扱う職人さんによっては台無しになってしまうこともあるので、やはり信頼できる業者さんに塗装工事をお願いすることが大切です。
腕の良い業者さんに理想通りの塗装をしてもらいましょう。

「外壁塗装の達人」は、外壁塗装に関する相談を承る無料のサービス機関です。
中立的な立場でご回答させていただいております。

※ご入力頂いた方全員に業界裏情報まとめ小冊子プレゼント中!
「外壁塗装の達人」は、外壁塗装に関する相談を承る無料のサービス機関です。
中立的な立場でご回答させていただいております。
Copyright©センターグローブ All Rights Reserved